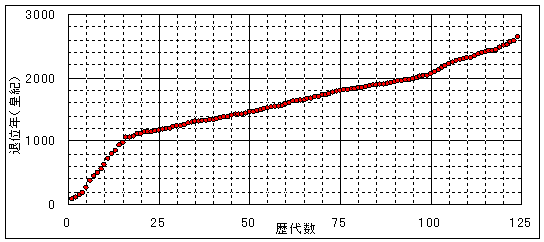
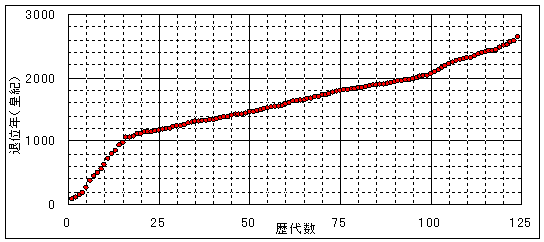
日本書紀の記述をそのままグラフ化すると第16代あたりに折点がでます。
古代天皇の年齢が高く、在位期間も長いのはどうしてでしょうか?
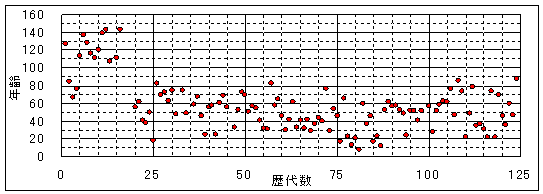
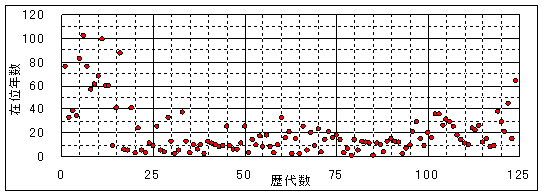
◎統計学的に極めて不自然です。
◎2660年に及ぶ歴史の流れの中でも特異な現象であり不自然です。
暦の違い
◎神武天皇〜安康天皇までは「儀鳳暦」が使われています。
◎雄略天皇〜持統天皇までは「元嘉暦」が使われています。
◎儀鳳暦は「日本書紀」編纂時に使われていた新しい暦です。
◎雄略天皇以降については記録が文書で残っていたものと推定されます。
◎口伝部分について儀鳳暦を当てはめたのではないでしょうか。
◎第20代と第21代の間には何か謎がありそうです。
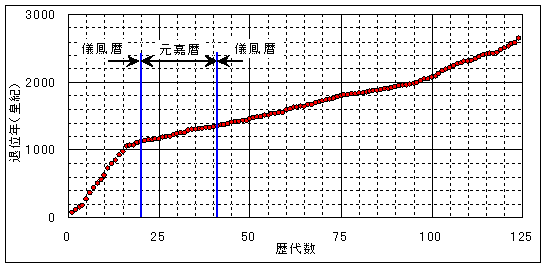
1年2倍暦の存在
◎「崇神天皇」から「雄略天皇」までの古代天皇の年齢を「古事記」、「日本書紀」
から拾ってみると右表のようになります。
◎多くの天皇が100歳以上の長寿を全うしており、150歳以上の天皇もおられます。
◎一般的に古代ほど平均寿命が短かったでしょうから、生物学的にも不自然です。
◎景行、垂仁、成務の各天皇が軒並み庚午年に薨去しているのも、不自然です。
◎表にはありませんが「武内宿禰」に至っては289歳という年齢すら出てきます。
◎しかし、この超人的な寿命を見て「紀記」の信頼性を否定するのは性急です。
◎背景に巧妙なからくりが潜んでいるものと想われます。
◎いつ頃まで1年2倍暦が使用されていたかが問題です。
◎別途検証しますが、第20代安康天皇までが1年2倍暦でした。
◎これは謎解きその2で示した暦の違いと一致します。
◎謎解きその1で示した折れ点は第16代あたりでしたが、第17、18、19代は兄弟
相続であり、第20代は暗殺されています。
◎第20代までは年齢を半分にして考える必要があります。
