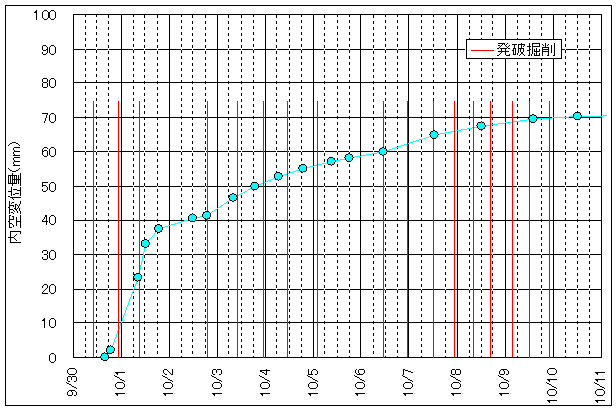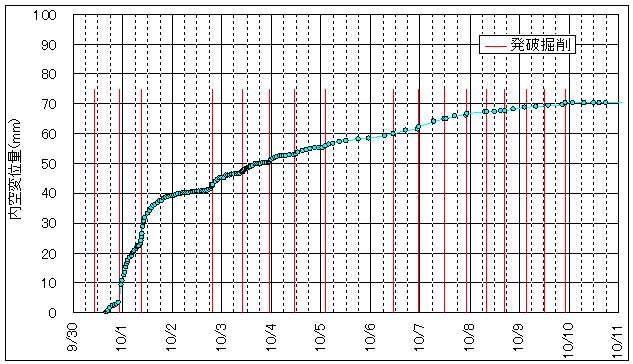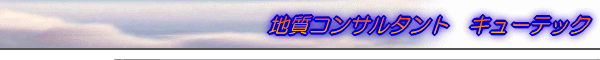- 初めての内空変位計測
- 昭和52年、上越新幹線中山トンネルにおいてNATMが導入された当時は、トンネル施工時の計測は非常に珍しいことでした。
- 現在ではトンネル施工時の計測は常識となっています。しかし、当たり前であるが故に、計測の本来の主旨が忘れられていることがあります。
- ここでは私にとって初めての内空変位計測データを示します。
- 内空変位測定結果は次のような指数関数的なグラフになることはよく知られています。
- 通常は計測頻度が1日1回から2回程度ですので一般的には次のようなグラフが得られます。
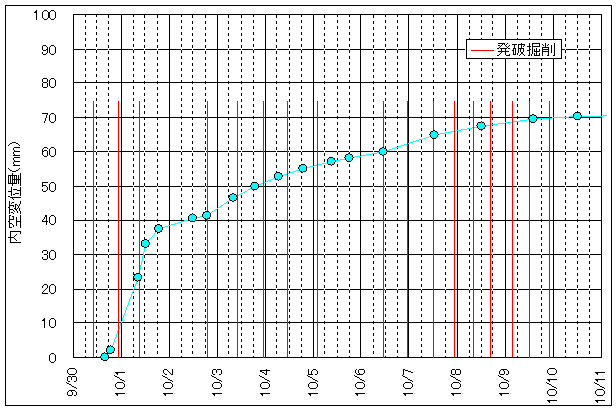
- しかし、初めて計測に挑戦した当時はどのようなグラフになるのかも全くわかりませんでした。
- テープエキステンソメータを抱え、無我夢中でした。
- 計りだしたら面白くてやめられなくなり、発破直後は5分おきに計ったりしました。
- グラフを見ていただければわかるとおり、トンネル内に泊まり込み、昼夜の区別無く計測に没頭しました。
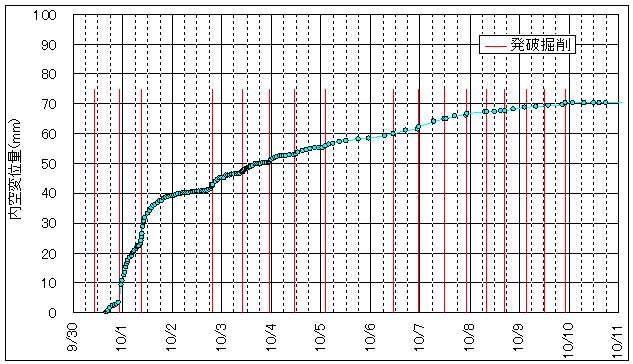
- 1m掘削する毎に指数関数的グラフが繰り返されていることがわかります。これは当時の大きな発見でした。
- 持ち込んだ食料をネズミに食べられてしまい空腹に耐えながらの計測でしたが、ゼネコンの方が弁当を差し入れてくださり助かりました。
- 自動計測など全くない時代に、このような内空変位グラフは恐らく二つと無いことでしょう。
- 20代前半の若さゆえ出来たことでした。青春時代の思い出です。
- 本計測データを用いた解析が次の論文に掲載されています。
- 土屋 浩(1983) トンネル掘削に伴う壁面の変位量予測手法;応用地質調査事務所年報No.5
P.103